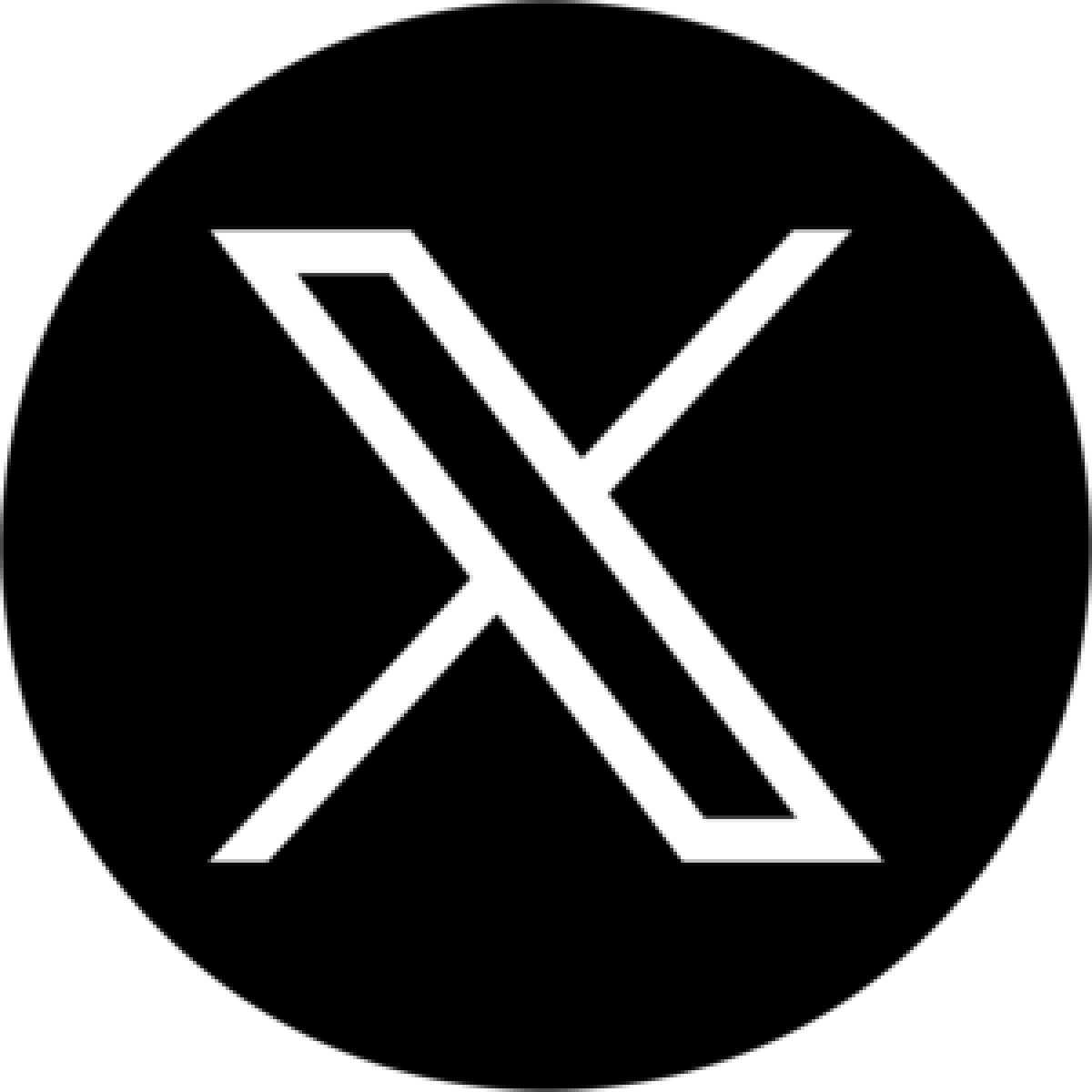2024年9月4日、SHIFTが手がける技術イベント「SHIFT EVOLVE」より、「エンプラ企業DXの成功事例(もっとよくなる日本のIT vol.1 )」と題された対談イベントが開催されました。
今回は、アメリカで最先端の技術を開発しながらSHIFTの技術顧問も務めている川口 耕介氏と、日本のエンタープライズ企業でDXの導入に成功した小野 和俊氏によるディスカッションです。
過去にスタートアップで活躍していた小野氏からみて、エンタープライズ企業のDXを進めるにあたってどんな工夫をしたのか。
あらゆる文化が異なるなかで、どのように関係者とリレーションを築きあげたのか。ざっくばらんな経験談をもとに、川口氏が切り込んでいきました。
※1時間半近いセッションだったため、特に印象深かった箇所をピックアップしてお届けします。
※SHIFT EVOLVEとは?SHIFTグループが主催する技術イベントグループ。 エンジニアコミュニティから技術をEVOLVEしこう、という想いで運営し、メンバー登録者数は3,200人を超える(2024年9月時点)。他社を招いた先進的なディスカッションなど、開催予定のイベントは以下よりチェック。 https://shiftevolve.connpass.com/
-

小野 和俊
株式会社クレディセゾン 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 CDO
1999年、大学卒業後、 Sun Microsystems株式会社に入社。米国本社でのJavaやXMLでの開発を経験した後、2000年に株式会社アプレッソを起業し、エンジェル投資家から7億円の出資を得て、データ連携ミドルウェア「DataSpider」を開発。SOFTICより年間最優秀ソフトウェア賞を受賞する。2004年、ITを駆使した独創的なアイデア・技術の育成を目的とした経済産業省の取り組み、「未踏ソフトウェア創造事業」にて「Galapagos」の共同開発者となる。2008年より3年間、九州大学大学院「高度ICTリーダーシップ特論」の非常勤講師を務める。
2013年、「DataSpider」の代理店であり、データ連携ソフトを自社にもちたいと考えていたセゾン情報システムズから資本業務提携の提案を受け、合意。2015年にセゾン情報システムズ(現セゾンテクノロジー)の取締役 CTOに就任。当初はベンチャー企業と歴史ある日本企業の文化の違いに戸惑うも、両者のよさを共存させ、互いの長所がもう一方の欠点を補っていく「バイモーダル戦略」により企業改革を実現。2019年にクレディセゾンの取締役CTOとなり、2020年3月より現職。
-

川口 耕介
株式会社SHIFT 技術顧問
・Sun Microsystems在籍中にCIツールの草わけJenkinsを開発
・米CloudBeesにてCTOとしてJenkinsや関連サービス・製品の発展・普及を推進
・SHIFTの技術顧問に就任(2019年)
・AIを使って自動テストの効果を改善するサービスLaunchableを米国で立ちあげ(2020年)
・同サービスの日本法人Launchable Japanを立ちあげ(2020年)
・CloudBees、Launchableを買収。現職は co-head of AI, CloudBees (2024年)
https://www.launchableinc.com/
目次
セゾンテクノロジーの「日本人らしい戦い方」に感銘を受けて会社に残りつづけた

川口:2000年に起業したアプレッソが、セゾン情報システムズ(現セゾンテクノロジー)にM&Aされたということで、僕のまわりではそういう場合、ロックアップ期間後すぐに会社を辞めていくパターンが多いのですが、小野さんが取締役 CTOとしてグループに残る決断をされたのはなぜでしょうか?
小野:僕自身、環境が違いすぎてまわりからすぐに辞めると思われていましたし、それこそ最初はいままでのやり方と随分違うなということで違和感やもどかしさみたいなものがありました。
でも半年ほどいっしょに仕事していくなかで、そういった僕とは違うやり方の合理性みたいなことに気づきまして、これはこれですごく価値のあるやり方だなって思ったんですよね。
つまり、セゾンテクノロジー(旧セゾン情報システムズ)のやり方ってものすごく安定性・堅牢性重視なんですよ。
具体的にお伝えすると、HULFTという製品は「メインフレームのハードウェアよりも障害発生率が低い」ってことをプライドにしてたんですよね。
自分たちは社会インフラの本当に重要なところに使われているから、バグを一個でも出したらアウトなんだよと。「ワンストライク・アウト」ってのがかけ声になっていて、実際にバグがないんですよね。
それをみて、例えばウォーターフォールとアジャイルのどっちがいい/悪いではなく、プロジェクトによって切りわけていくのが答えであろうということで、そこに取り組みたいと思ったのが理由ですね。
すごく日本人らしい戦い方といいますか、日本人の特性をうまく強みにつなげている戦い方だなと、単なる面白さを超えてすごいなと思いましたね。
川口:ある種「未知なるもの」に対する好奇心が強いのかなと感じましたが、それはいつからですか?
小野:原体験みたいなものでお伝えすると、大学のときに弁論部の部長をやっていまして、そこで競技ディベートに参加していました。
競技ディベートって、ある議題に対する意見として、イエス/ノーどちらの立場からでも議論できるよう綿密に準備するんです。
なるほどなと思ったのが、ほとんどの人って自分の意見の反対の立場の考えをあまり調べていないよなと。
反対の意見も理解すると、意外と自分の意見も変わったりもする。一旦自分の考えを一切忘れて、全力で反対の立場の意見を考えてみるみたいなのは、大学のころから訓練されていたと思います。
「絶対に否定しない」ことだけはずっと守ってきた
川口:セゾンテクノロジーの取締役 CTOから2019年にクレディセゾンの取締役 CTOに移られたということで、その際のクレディセゾン側の人たちはどんな反応だったのでしょうか?
小野:正直、面白くないと思われていた方もいらっしゃったと思いますが、それ以上にDXを進めなければという想いの方が先行していた印象です。
当時のクレディセゾンで社内のシステム開発の内製を進める際、MacBook Pro購入にしても、ビルドでもってくるライブラリに差分があったりしても、その都度、紙の申請書を書いてほしいと。
これは正直、開発するなっていわれているのに等しいわけですよね。
でもそのまま物わかれに終わっちゃうわけにもいかない。だから、実際にダメだといっている人たちのところまで行って、なぜダメなのか、どうしたら折りあいがつくかを探っていきました。
そうやって丁寧に膝を突きあわせて話すと、意外と着地点ってあるんですよね。誰も否定せず、相手が考えるリスクを回避して、リスペクトした形で僕らがやりたいこともできる。
それを一つひとつやっていけば、あまり排除される形にはならないんじゃないかなと思っています。
川口:すごくエネルギーを使いますね。CTOとしてはやく成果を求められる状況で、なぜそんな神業みたいなことができるんですか?
小野:ひとつだけ、セゾンテクノロジーに2013年にイグジットしたときからずっと一個だけ守ってることがあって、それが「絶対に否定しない」ことなんですよね。
相手は絶対に何か合理性/背景があってそうしているはずだという前提があって、否定しなければ大体のことはうまくいくはずと思っています。別に神業とかではなく、すごく基本的なことなんですよね。

体験とセットで自己紹介することの大切さ
川口:いろんなリーダーシップの形があると思いますが、小野さんが、ご自身のやり方に自信をつけていった過程って何かありますか?
小野:自信とは少し違うかもしれませんが、体験とセットで自己紹介しあうことって大事だなと思っています。体験って情報量が圧倒的に多いわけじゃないですか。
例えばサッカーで考えてみても、ルールブックを読んでできるものじゃなくて、やってみていろんな情報からエッセンスを学んでいくんですよね。
クレディセゾンでもいっしょで、例えば先ほどのHULFTのアセンブラコードを一回も書いたことがなかったので、ライブコーディングみたいな感じで、担当の方に書いているところをみせてもらったんですよ。
「次もしかして、ここにこういうの書き込んだら、こうなったりします?」「ご明答!」とかやりながら、徐々に仲よくなっていって、いまはいっしょに飲みにいくような関係性なんですよね。
でも少し前にいわれたのが、「最初にやってきたときは本当に嫌いだった」「アメリカ帰りの若造がどうせ俺たちのことフルボッコにして、俺たちの村とか畑を焼きにでもきたんじゃないかと正直思っていた」と。
実際にお互いやってみせようよっていうのをコミュニケーションの一つのプロトコルにして進めていくと、変にぶつかることはないなという意味で、自信はついていったと思います。
川口:まさにバイモーダル戦略ですね。
小野:一点、ここで注意すべきことは、ただの「交流」にしないことです。
バイモーダルって、モード1とモード2の混在といわれていまして、モード1が日本企業で伝統的に進められてきたような安定性重視みたいなもので、一方でモード2はスタートアップ的なスピード感で個人技をよしとするような感じなんです。
つまり、この2つって基本的には相容れないところがあります。自分の正義が、相手のやってることとまったく逆になりますからね。
先ほどお伝えしたようなアプローチもなく、ただ交流すればわかりあえるはずだ、っていうのは絶対に違いますね。交流すると、むしろ喧嘩すると思いますよ。
川口:おっしゃる通りですね。それにしても、どうやったら小野さんのクローンってできるんでしょうね? 小野塾とかつくらないんですか?
小野:どうなんでしょうね、そもそも僕のやり方はあくまで僕のパターンであって、一つのサンプルとかリファレンスのやり方としてはいいと思うのですが、そこから「自分だったらこうする」くらいの取り入れ方でいいのかなとは思います。
川口:ここは守破離の「守」だと思うんですよね。スタート地点としてはやはり「俺はこうやったんだぞ」っていう体系を提示して、その合理性を信じて学ぶっていうことが間違いなくありますよね。
小野:それはあると思いますよね。やはり、何もないときに自分独自のやり方が突然生まれるとかは絶対にないはずですから、どこかでまずはテキスト的なものや先輩から学ぶといったプロセスは、もちろんあっていいと思います。
一方で、まずはやってみる/動かしてみる、からの学びもあると思うんですよね。たとえば電波新聞社のベーマガ(マイコンBASICマガジン)ってあるじゃないですか。
当時ってあれぐらいしかなかったと思うのですが、ある意味で個人が書いたものを投稿しているだけなわけで、大学の先生に教わるとかそういった類の学び方じゃないですよね。
独学でやり方を学んでいって、その後にGoFのデザインパターンとかみて、「自分があのときどうやって共通化しようかなと思ったやり方って、なんかこのパターンでカタログに入ってて、こっちの方がけっこうよくできてんじゃん」っていうふうになるわけですよ。
こんな感じで、まず自由にやってみて、その後型のすばらしさに感銘を受けるという流れもあると思うんですよ。ですから、どっちの道もありそうな気はしています。

キーワードとしての「ストーリーテリング」
川口:そんな小野さんは、これからどうしていこうみたいなのはありますか?
小野:どうなんでしょう。中長期的なプランとか考えないタイプなんですよね。
あんまり不安も感じてなくて、日本の事業会社がうまくITを取り入れられてこなかった部分に対して、いまやっていることにけっこうしっかりとした手応えを感じていてですね。
もちろん、まだまだToDoはたくさんあるのですが、やっていて楽しいしやりがいもあるので、先のことはあまり考えていないですね。
川口:楽しいって大事ですよね。自発性が鍵といいますか。
小野:たぶんキーワードとして、ストーリーテリングがあるんですよね。
ハーバード・ビジネス・レビューで2年半くらい前に「データコミュニケーションのコアタレント」というタイトルで記事になったんですけど、企業のデータドリブン経営に向けて8パターンほどのロールがあって、そのうちの一つに「データストーリーテリング」というのがあるわけです。
データのみせ方ってものすごく恣意的にできちゃうなかで、しっかりと背景/趣旨をメンバーに伝えていくみたいなところが大事だという話なんです。
なぜこういうことをやってみるのかというストーリーテリングがちゃんとできていれば、合意が得られることも多いと思うんです。まあ僕自身、オーガニックにはめちゃくちゃ陰キャでしゃべらないタイプなんですけどね。
川口:周囲はそうはまったく思っていないと思いますよ。話すのは一級だなと。
小野:学生のころの訓練や職業上のロールの結果、話す力が身についてしまっただけだと思います(笑)全部人工的な一級ってことですかね。
パネルディスカッションの他パートや、動画全編をご覧になりたい方はこちら
―――さまざまなテーマでイベントを開催中のSHIFT EVOLVE。 今回は「もっとよくなる日本のIT」と題したシリーズ第一弾でした。次回以降もぜひお楽しみに。
3,200名を超える登録者数!技術イベントSHIFT EVOLVEをチェック
(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)