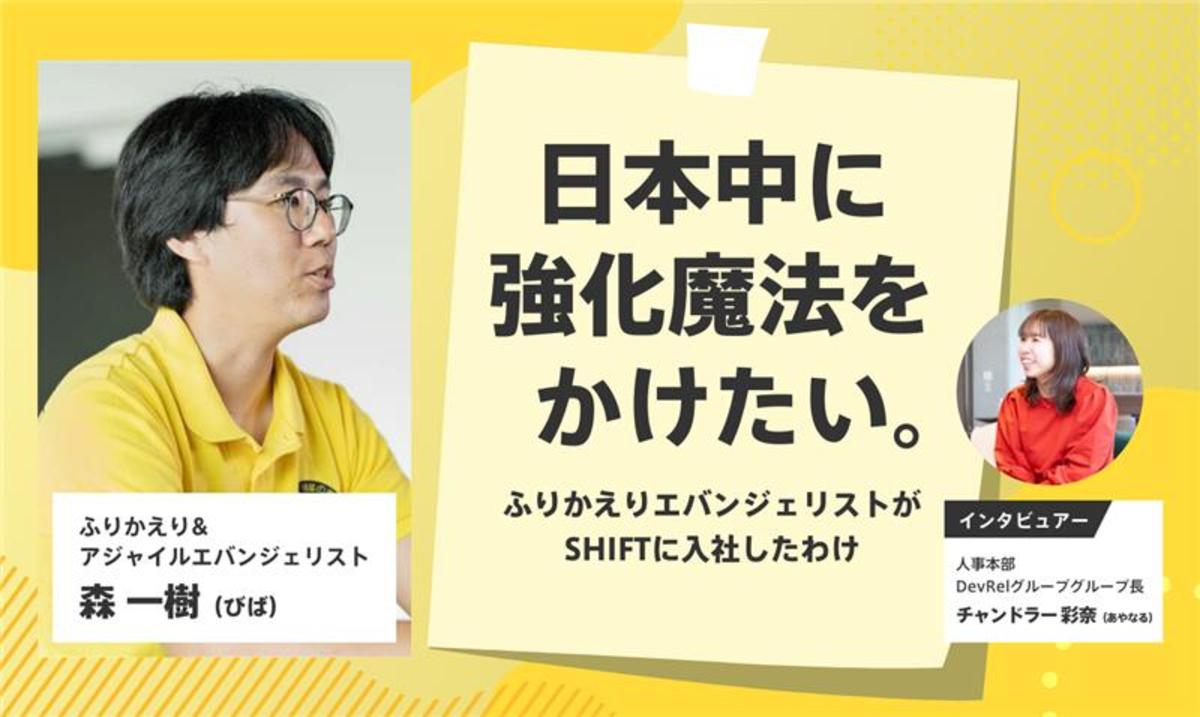「目の前の課題を何とかするために必要なものをかき集め、自分なりに組み立てて―――そんなふうにずっと現場でやってきました。それで自分のことを”野生のエンジニア”って呼んでいるんですけど」
そう少し照れくさそうに笑うのが、今回の記事の主人公、大﨑です。
一エンジニアとしてキャリアをスタートし、経営マネジメントまで経験した彼の強みは、「技術」と「マネジメント」の二刀流であること。SHIFTではアジャイル推進部に所属しPMを担っています。
当初のQA参画から、現在は開発工程の改善にまで踏み込む彼の歩みについて話を聞くなかで、PMとしての本質的な役割が見えてきました。
記事後半では、「快適に働くこと」を大切にする彼が思う、SHIFTの働く環境についてもお届けします。
-

アジャイル推進部 大﨑
2007年から専門学校を卒業して、ゲーム業界で一エンジニアとして入社。その後、業界の荒波のなかで所属企業のさまざまな統廃合が発生。その中なかで、ゲームディレクター、CTOも経験。2020年に医療用検査機器業界で、品質管理や全社のDX化推進を担当。2023年にSHIFT入社後、通信業界案件のPMに従事。社内AWARDでの部門特別賞やキャプテン賞の受賞歴も。
目次
試行錯誤の末、イテレーション型ウォーターフォールの開発に
――まずは、入社後から現在にわたって携わっているという案件について教えていただけますか?
大﨑:通信会社様のワークフロー自動化プロジェクトです。全国に点在する機器から集められる膨大な情報を起点としたオペレーション、これを可能な限り自動化することが我々のミッションです。
――ワークフローの自動化ですか。
大﨑:そうですね。集まった情報やアラートごとに対応手順が決まっているのですが、人間が対応するには障害のリスクやコストの問題がつきまといます。
そこで自動化のためのシナリオをたくさん実装していくというのがSHIFTの主なミッションです。
この「シナリオ開発」は少し特殊で、普通の開発モデルをそのまま適用しにくい部分があるため、開始当初はプロジェクト全体が手探りの状態でした。
――手法としてはアジャイル開発なのですか?
大﨑:はい、アジャイル手法の一つである「イテレーション」です。1本のシナリオの開発は厳密に工程が管理されていて、ウォーターフォール的で、およそ1月に1回それらをまとめてリリースしています。
自動車工場のように、工程や処理の順番がきちんと決まっていて、その点ではウォーターフォールと同じですが、それらをまとめて、品質担保のスコープを狭めつつ、ニーズに対するレスポンスの担保を両立するために小さな単位で繰り返すことからイテレーション型といえます。
シナリオ一つひとつが、車一台一台に相当するイメージで、このプロジェクトの特性に合わせた形になっています。
アジャイルは多様なやり方が許容されるフレームワーク、あるいは考え方なので、そのなかでもプロジェクトにもっとも適した形を模索しています。
――このプロジェクトでの大﨑さんの役割はどのようなものですか?
大﨑:当初、私はQAメンバーとして参画しましたが、いまは開発工程全体のプロセス改善や品質担保を担当しています。
具体的には、工程のなかでレビューの観点が二重化している部分や、前工程と後工程で重複するテストをしているなどの無駄を発見し、責任分解点を明確にして効率化するといった活動を行ってきました。
役割が広がったきっかけは、工程の巻き戻りが多く非効率だったため、「見直しを任せてもらえませんか」とお客様に提案したことでした。
そこから、プロセス全体を俯瞰して問題点を特定し、改善策を提案・実行していくようになりました。
――その過程は後ほどくわしく伺うとして、結果的にSHIFTからの参画規模が大きくなっていった?
大﨑:そうですね。現在はSHIFTから約20名が参画し、QAだけでなく技術や管理領域でプロジェクトのコアなポジションを担うメンバーも多くなっています。

仲間と強みを活かしあうから、課題解決という本質に迫れる
――この案件を通して感じた、SHIFTの強みを教えてください。
大﨑:メンバーが非常に優秀であることですね。これほど楽にプロジェクトマネジメントをしたことがないというくらい、彼らの働きぶりに助けられています。コミットメントが高く、生産性向上に寄与している人が多く集まっていると感じます。
私は問題の発見・解決に強みがあるのですが、定型業務は正直得意な方ではありません。メンバーは、そのあたりをすごくサポートしてくれていて。
「これはやっておいてほしい」という期待値を、メンバーは当然のように超えてくれます。
まるで「大﨑さんは自分がやるべきことをやってください」とメンバーにいわれているような感覚です。いい意味でありのままの自分を認めてもらえていると思います。
その結果、私は本質的な課題の言語化や見える化、仮説と検証といった部分にフォーカスできる。どうすればプロジェクトがうまく進むか、品質を向上できるかといった点に対し集中させてもらっています。
――具体的にどのように課題を発見、解決したのでしょうか?
大﨑:先ほど少しふれましたが、開発プロセスの非効率性から、どこかに大きな課題があるのは間違いありませんでした。
私はそれを一メンバーとして特定し、お客様やプロジェクトメンバーに対して証明する必要がありました。
具体的なアプローチとしては、まず前工程の業務内容をヒアリングし、成果物を確認して作業内容を理解します。そして現状のプロセスを1つずつ確認し、インプット、アウトプット、作業内容、品質担保の方法や環境が整っているかを精査します。
その結果見えてきた現在の開発ルールと問題点の因果関係を資料にまとめ、起こっていることを見える化します。それまでは自分の担当領域外のことは見えず、ただ何かがおかしいと関係者がふわっと感じていたところを、全体像と問題点についてみんなが共通認識をもてるようにしたということです。
問題点が共有されれば、自然発生的に関係者から改善案が出てきます。あとはそれらの意見から課題を整理し、関係者全員の懸念点を潰してから、新しいやり方へ移行していきました。
――「定型的な役割」を越えた動き方をされているように見えます。
大﨑:役割の定義を理解したり学んだりすることは重要ですが、アジャイルにおけるPMという仕事の本質は管理することではなく、支援促進することです。
プロジェクトに関わる全員が幸せになるにはどうしたらいいか、開発効率を最大化するために、自分に何ができるか広い視野で行動しています。
このプロジェクトに関わる全員という表現には、プロジェクトに責任をもっているお客様のPMやその先にいる事業判断・投資判断を行うようなたちも方々も含みますし、正確に素早く決まったタスクをこなすことを求められる末端メンバーも含まれます。
したがって、レポートや成果分析のためのプロセス品質情報を残すという手間がかかることを徹底していくという一方で、そのうえで人がやらなくてもいいことはどんどん自動化を進めていくことにも同時に力を入れています。

「快適さ」を大切にしたい。働き方の美学
――大﨑さんは、働くうえで何を大切にしていますか?
大﨑:大切にしているのは「快適さ」です。私が働く理由は、楽しく幸せに生きたいから。
若いころは仕事でがむしゃらに成果を上げることを追いかけていましたが、いまは仕事を通じて、いつか引退してもいっしょに遊べる仲間、友人といえる関係性をつくることが非常に大事だと考えています。
仕事は出会いの場の一つであり、QOL(Quality of Life)を充実させるための手段だと思っています。
――SHIFTの環境は、大﨑さんが求める「快適さ」や価値観と合っているといえそうでしょうか?
大﨑:そうですね。実際、信頼できるメンバーといっしょに働けていて、上司との関係も良好ですし、人間関係も含めてSHIFTは私にとって居心地のいい場所になっています。
私は社内でメンバー同士を競わせるような社風は苦手なのですが、SHIFTは「みんなで頑張って、みんなでいい結果を出そう、みんなで幸せになろう」という文化があり、私の価値観と非常にマッチしています。
エンジニア単価の向上を全社的なKPIとしている点もその現れであり、革命的だと私は捉えています。売上規模だけを追うと、エンジニアや現場が疲弊したり、身の丈に合わないことをやりだしたりして、大きなリスクにつながることがありますから。
――革命的という言葉が出ましたが、ほかに「SHIFTは特にここがすごい」と思う点はありますか?
大﨑:制度や各種規則までを含めた社内のシステムが非常に洗練されている点ですね。
あげていけばキリがありませんが、例えば評価制度のディティールについて。
お客様からの評価でもある単価が個人の成績に反映される仕組みは他社でもあるとして、SHIFTの場合、単価を上げていくステップとして、社内検定「トップガン」が誰にとってもわかりやすい形で設計されています。
「学びの機会」「スキルに応じたチャンスの提供」さらに「実績で評価」という流れがセットで仕組化されている。逆に、私のように資格を取得していなくても、お客様への価値提供やビジネスインパクトに応じて評価もされますし、よくできているなと感心します。
こうした仕組みを考える経営陣は、私からは、合理的でかつ人間味があるように見え好感がもてます。例えば新しい制度の説明をしていても経営者の人となりが透けて見えるものだと思っていますが、意思決定の内容と説明のしかた、社内意見への対応などからそう感じます。
指摘を素直に受け入れ、必要な部分は対応しながらも、芯はぶらさない人たちだという印象をもっています。
――最後に、今後のご自身のキャリアについて考えていることを教えてください。
大﨑:私は「プランド・ハップンスタンスセオリー」という考え方を大切にしています。
目の前の仕事に精一杯向き合い、人との関係を築いていくと、必然的に期待が寄せられ新しい仕事につながります。それが「あなたにはこれが向いているということですよ」という、メッセージである可能性が高いと思っていて。
よほど自分の感覚と外れていなければ、目前の仕事を一生懸命やってみることが、自分を幸せにしてくれる仕事につながっていくだろうと捉えながら、自然とキャリアを積んでいけたらと思っています。
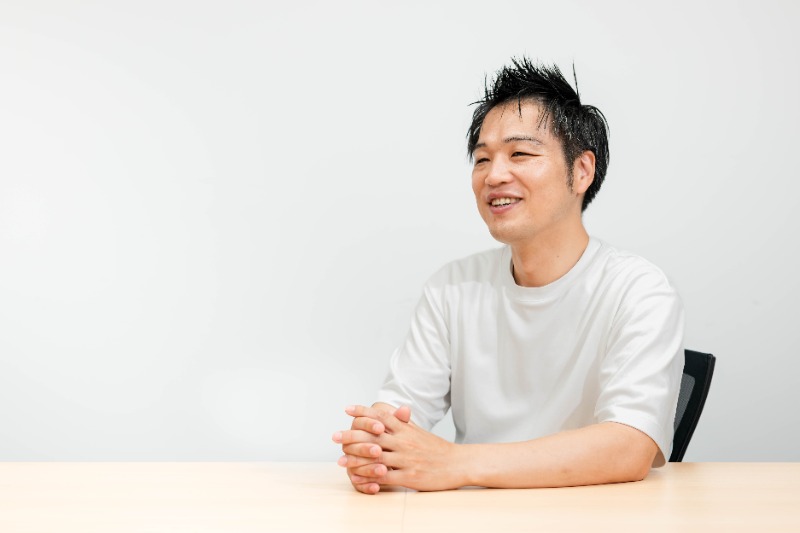
――本日はお忙しいなか、ありがとうございました!
(※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです)