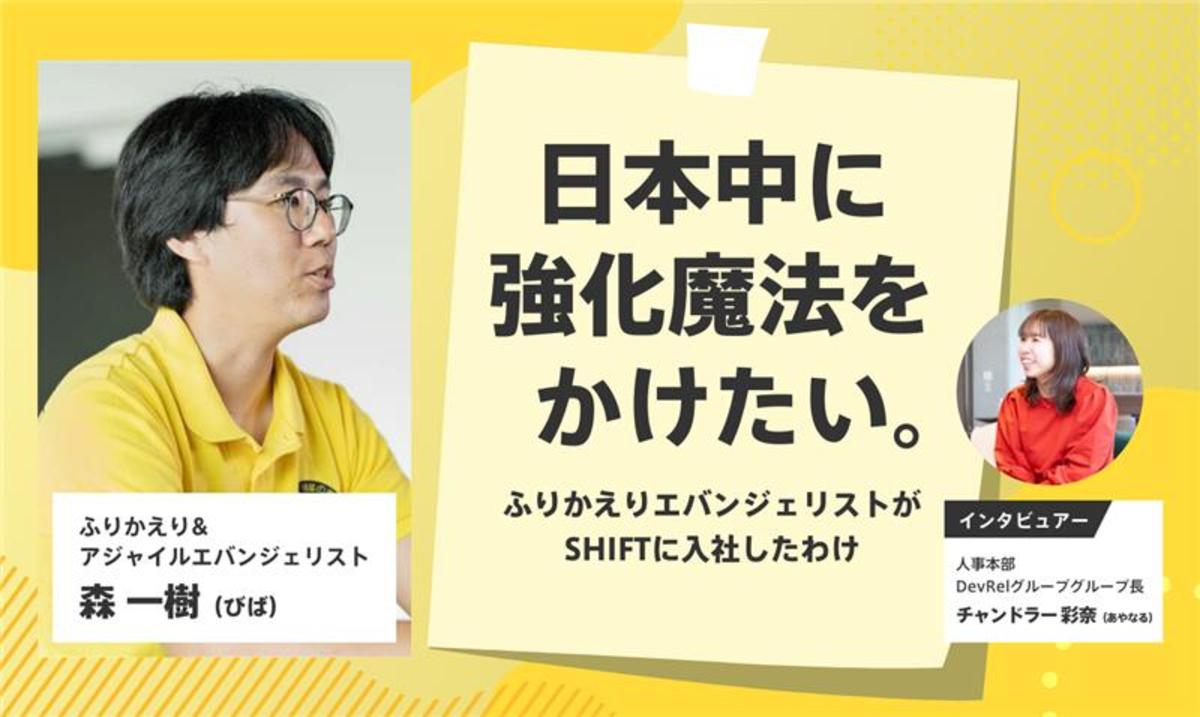2025年2月20日、SHIFT主催の技術イベント「SHIFT EVOLVE」にて、「アジャイルで実現する高品質なプロダクト(Agile in Motion vol.2)」と題されたセッションが開催されました。
品質保証のプロであるSHIFTならではの目線で、アジャイルに長年携わってきたゲストを招き、アジャイルの神髄に迫るという本シリーズ。
今回は、アジャイルを日本に広めた永和マネジメントシステムで取締役CTOとAgile Studioディレクターを務めながら、福井県DX推進アドバイザー(CDO補佐官)を務める岡島幸男氏と、ふくおかファイナンシャルグループでアジャイルを推進しながら、スクラムフェス福岡を運営する松﨑一孝氏を迎え、SHIFTのアジャイルコーチ・三品 正人が、行政や金融業界など高い品質が求められる現場でのアジャイル組織の工夫について掘り下げました。
本記事では、特に印象深かった箇所をピックアップしてご紹介します。
-

株式会社永和システムマネジメント 取締役 CTO / Agile Studio ディレクター(マーケティング責任者) 岡島 幸男 氏
Web・組込など、さまざまなソフトウェア開発とマネジメント、事業開発の現場を経て、現在は Agile Studioにて企業のアジャイル化を支援。 2022年1月より副業で福井県DX推進アドバイザー(CDO補佐官)。アジャイルを活用し自治体DXを推進すべく活動中。
著書に『受託開発の極意―変化はあなたからはじまる。現場から学ぶ実践手法』(技術評論社)ほか。 -

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ DX推進本部 内製開発グループ シニアエキスパート 松﨑 一孝 氏
アミューズメントゲームやスマホアプリの開発などを経て、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(FFG)に入社。FFGのデジタル戦略の起点となるデジタル戦略部(現DX推進本部)の立ちあげに携わり、内製開発の組織づくりを主導。プロダクト開発チームのスクラムマスターを担いつつ、社内に内製やアジャイルの文化を浸透させるための活動に従事。スクラムフェス福岡を開催するなど、地域のコミュニティでも積極活動中。
-

株式会社SHIFT アジャイルコーチ 三品 正人
10年以上にわたり、ゲーム会社でソフトウェア開発プロジェクトに参加。当初、プログラマ、マネージャーとして開発を経験するなかで、どうしたらエンジニアが幸せになれるか悩み、アジャイル開発に出会い、スクラムマスターとして開発に関わるようになる。その後はPMOとして社内プロジェクトにアジャイル開発を推進する活動を行う。
SHIFT入社後は、案件ではスクラムマスターとしてアジャイル開発支援を行いつつ、社内ではアジャイル啓蒙活動、スクラムマスター育成を行う。1人でも多くのエンジニアが幸せに働けるように活動をしている。
目次
スクラムチームが品質に責任をもち、テストも実行する
松﨑:前職はゲーム会社で、ゲームをつくっていたのですが、そこでは割と「自分でつくって、自分でテストして、世の中に出していく」という流れが当たり前でした。
そんななか、いまの会社に転職して、実装チーム/テストチーム/運用チームみたいに組織がわかれていることに違和感を覚えまして。
当然、スクラムチームが品質にも実装にも責任をもつべきだということで、そのような方針で自分がみている開発組織を運営しています。
岡島:転職直後にそういう提案をすると、なかなか理解を得られにくいんじゃないかと思うのですが、いかがですか?
松﨑:そもそもゼロからはじめた組織だったので、「そういうものなんです」という形で、ちょっとずつ改善しながら進めていきましたね。
転職から7年ほどたち、いまでもまだ脆弱性診断など第三者機関によるテストが残っているところもありはしますが、基本的には自分たちで全部やるというのがベースになってきています。
三品:僕ももともとゲーム会社だったのでよくわかります。なんで当たり前のことができない状態でテストとしてあがってくるのか、と感じたことはありますね。
僕たちの場合、不具合のチェックだけでなく、ゲームの手ざわり感みたいなところも自分たちでチェックしていました。
岡島:アジャイル×品質というのが今回のテーマですが、「アジャイルだからより高品質を目指せる」ということはあると思いますか?
松﨑:いまだにウォーターフォールのほうが品質が高いという声もたまに聞きますが、実際にやるテスト自体はアジャイルでもウォーターフォールでも変わらないですし、むしろアジャイルの場合はスプリントごとに品質チェックをするので、不具合がはやくみつかることも多いですね。
岡島:もちろん、短いスパンでリリースをするために、やるべきことをやっていないで品質が下がるという話があるかもしれませんが、それはそれでまったく別の話ですからね。
三品:アジャイルで短いスパンでリリースをしていくにあたって、品質を担保するにはチーム内でテストもやるしかありません。
従来の手法にとらわれずに、どうやったら高品質にはやくリリースできるのかを問いつづけないといけないと思いますね。
QAを上流工程から巻き込み、1スプリント目から品質にこだわる
三品:僕からは、「スクラムチームのなかにQA専門の人を入れればいいんじゃないか」という観点でのお話をさせていただきます。
ここまでお話しいただいたとおり、理想は開発エンジニアがテストをやることだと思うのですが、自分が設計したシステムに対してバイアスがかかってしまい、想定外の行動ができない可能性もあるのではないかとも感じています。
そういった意味でも、QA専門のメンバーがいるといいなと、SHIFTに入ってから思うようになりました。実際にSHIFTではそういうサービスを展開していますからね。
じゃあ、チームに入り込む「アジャイルQA」の動き方はどうなのかというと、基本的には計画段階でいっしょにゴールの状態を確認し、スプリント開始と同時にテストケースをつくり、エンジニアが「できた」といったらすぐにテストを実施して不具合を報告する。
こんな感じで並行して動いていくような存在のイメージです。
とはいえ、短いスプリントでテストをするのがむずかしいケースも多いと思うので、できるだけ自動化するか、できるだけそもそものバグをつくらないようにすることが大事になってきます。
特に後者に関しては、マインドを変える必要があるなと思っていて、ウォーターフォールの場合は「いかに多くのバグを潰すか」が大事ですが、アジャイルの場合は「そもそものバグをいかに減らすか」が大事になってくると考えています。
そのうえで、上流工程であればあるほどバグを直すコストは低くなるので、なるべくはやい段階でバグをみつけることができるように、QAを上流工程から巻き込んで1スプリント目から品質にこだわることが重要だと捉えています。
松﨑:自分のなかの理想でいうと、チームにQAの知識を身につけてもらい、開発をしてもらうことだと思うのですが、チーム内QAから開発チームにフィードバックはするものでしょうか?
三品:もちろんしますし、そこが一番大事だと思っています。チーム全体で品質を上げることが重要なので、チームでいっしょに考えていけるように、品質面でリーダー的に動ける人がアジャイルQAになるというイメージです。
松﨑:となると、最終的にQAがチームを卒業するということもあるんですか?
三品:実際にそういうプロジェクトもありました。QAコーチ的に動いて最終的にチームから卒業していかれましたね。
松﨑:それが本当に理想ですね。品質のことを伝授していって、最終的にはQA担当がいなくても開発者が品質を担保しながら開発できるようになるという。
岡島:ここで参加者からのコメントです。「開発が遅れるとテストに必要な時間が確保できません。どのような対策方法があるでしょうか」ときているのですが。
三品:最初からうまくいくことは少ないので、いったん失敗を受け入れて、なんでできなかったのかを振り返るのが王道ですね。
あとは設計だけじゃなくて、テストをして修正して不具合がなくなった状態になってこそスプリント完了なんだよ、という認識に変えていくことが大事だと思います。
岡島:「テスト設計におけるテストケースの洗い出しや標準化を、どのように行っていますか?QAはなぜ不具合に気づけるのでしょうか」という質問もきています。
三品: SHIFTには年間約4,000プロジェクトへの参画を通じて培った「テスト標準観点」があります。
仕様書などのドキュメントがない場合でも、システムやサイトの種類、各種機能に応じて、こういったテストが必要だというのがノウハウとして蓄積されています。
部門横断チームで、組織的に品質を実現する
岡島:3つ目のテーマは「部門横断チームで、組織的に品質を実現する」ということです。
弊社の仕事は割と大規模で、省庁からの規制がある業態のものが多いのですが、例えば金融機関でのシステム開発の現場の声を聞いていると、いろんな工夫がみえてきています。
例えば、最初は機能ごとに組織がわかれてつくっていた状況が、規制当局への対応を細かく考えていろいろと試していくにつれて、徐々にワンチームになっていくことが確認できています。
また、そのようなシビアなシステムをつくっていくと、内部品質を高めることに力を入れた方がうまくいくという感覚もできてきました。
つまり、基準を満たす標準化された「正しい」コードを書くように教育をするということです。
基準を満たすコードを書いていくために教育機会をかなり提供することで、結果、外部品質も高まっていく。
もちろん、一朝一夕にできるような話ではないのですが、ある程度のトップダウンも交えながら、組織的にそのような文化をつくっていく必要があると考えています。
三品:いまのお話を伺って、一番大事なのはバランスだと感じました。
ベテランと中堅と新人がバランスよくいるチームがいいと思っていて、新人がいるからこそベテランと中堅が教えなきゃいけなくて、教えることで自分たちも学ぶことにつながります。
新陳代謝も働くので、バランスがいい方がチーム全体としてうまく機能する印象です。
岡島:そうですね。あと、メトリクスとか数字面も大前提として必要になってくるのですが、現場に聞いてみると、意外とそれに追われている様子はなく、それよりも情報共有や勉強会など、品質を上げるための取り組みに力を入れている印象で、そこが面白いなと思いました。
けっこうここはポイントかなと思っていて、これらの活動がしやすくなるための環境づくりへの注力は大事だなと感じています。まあ、鶏が先か卵が先か、みたいなところはありますけどね。
三品:結局アジャイル開発ってコンテキストによって変わってくるし答えもないと思っていて、いまおっしゃったようにメンバー同士を横でつなぐことで、アジャイル文化を浸透させていくコミュニティとして機能するようになりますよね。
岡島:あと先ほどのプロジェクトだと、一番業務に詳しい方、実質的なPOの方が、普段からサービスをよくさわってくれているのも大きい気がします。
2週間に1回のレビューの場だけでなく、普段から確認をして、悪いと思ったら都度指摘するという。けっこうそういうところも、総合的な品質の向上に寄与していると感じますね。
三品:POが製品・サービスに愛情があるの、すごく大事ですね。
参加者からのご質問
―――ここからは参加者からのご質問になります。AI関連の内容が多く、まずはこんな質問をいただきました。
「今後アジャイルにAIは不可欠になってくると思いますが、その活用と品質への向き合い方について。AIで生産量が増えたぶん、レビューやテスト設計などがボトルネックになりえるのではと考えています。」
松﨑:実際にAIを使って開発されていますか?うちはまだ、「これから導入していこうぜ」っていう段階です。
岡島:うちはけっこう使っていますね。大きくは2パターンありまして、コード生成支援としての使い方と、ユーザーストーリーをつくるときの壁打ち相手としての使い方です。
いただいた質問について、たしかにあるとは思いますが、精度がどんどんあがってくるはずなので時間が解決するのかなと思っています。
三品:コード生成はAIに任せて人間はレビューするだけという世界になって、極論1日単位でスプリントがまわるみたいな未来もありえるかも(笑)。
いずれにしても、アジャイルとかスクラムって、ここ20年ではあまり新しい動きがなかったと思うので、このあたりで大きな変化があるかもしれませんね。
―――三品さんにダイレクトに質問がきています。「AI活用により、若い人はますますスキルが落ちそうな気がする。AI時代の品質保証をどう考えられていますか?」
三品:別にそれでいいと思いますよ。何かが新しいものに置き換わったときには、昔のものはなくてもいいですよね。現時点で必要とされている知識がなくなることを、過度に恐れる必要はないかなと思います。
たしかに、細かいところを知っていればいざというときに使えるのでしょうが、そういうことを気にするよりも、新しいものを使ってどんどんと生産性を上げていくことに注力した方がいいのかなと思います。
もちろん、AI時代になっても一部は人による判断は残るとは思いますが。
イベント全編をみたい方はこちら
―――さまざまなテーマでイベントを開催中のSHIFT EVOLVE。次回以降もぜひお楽しみに。
3,900名を超える登録者数!技術イベント SHIFT EVOLVEをチェック
※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです