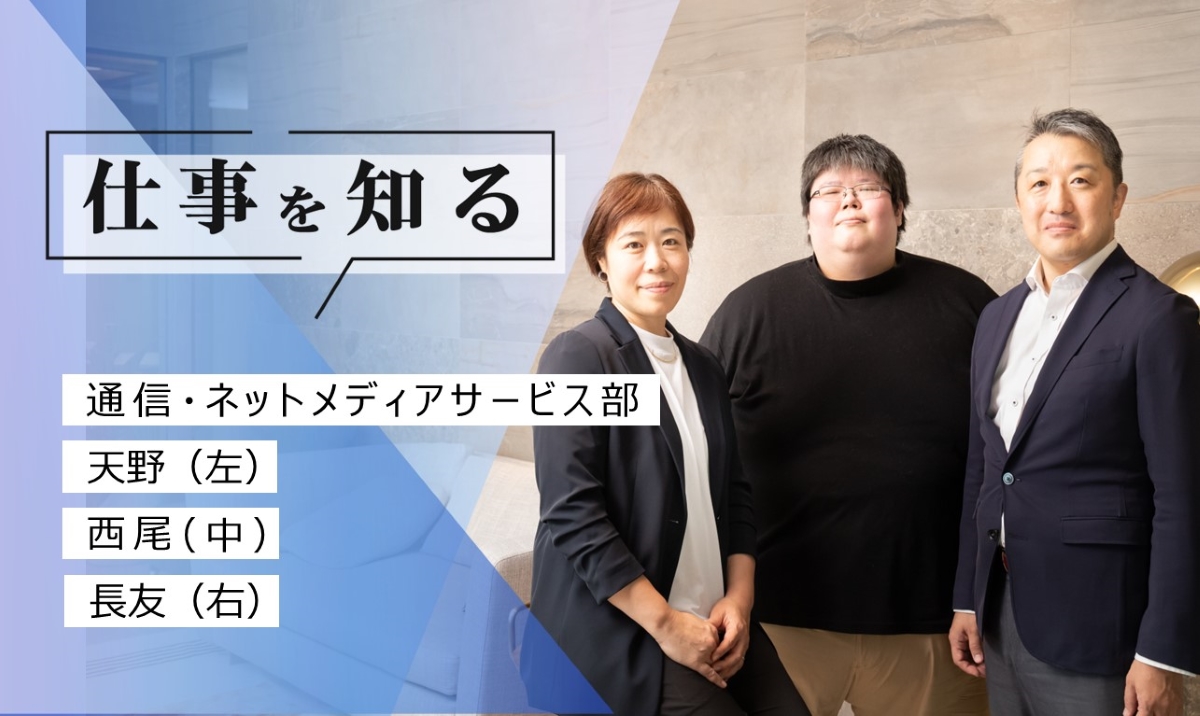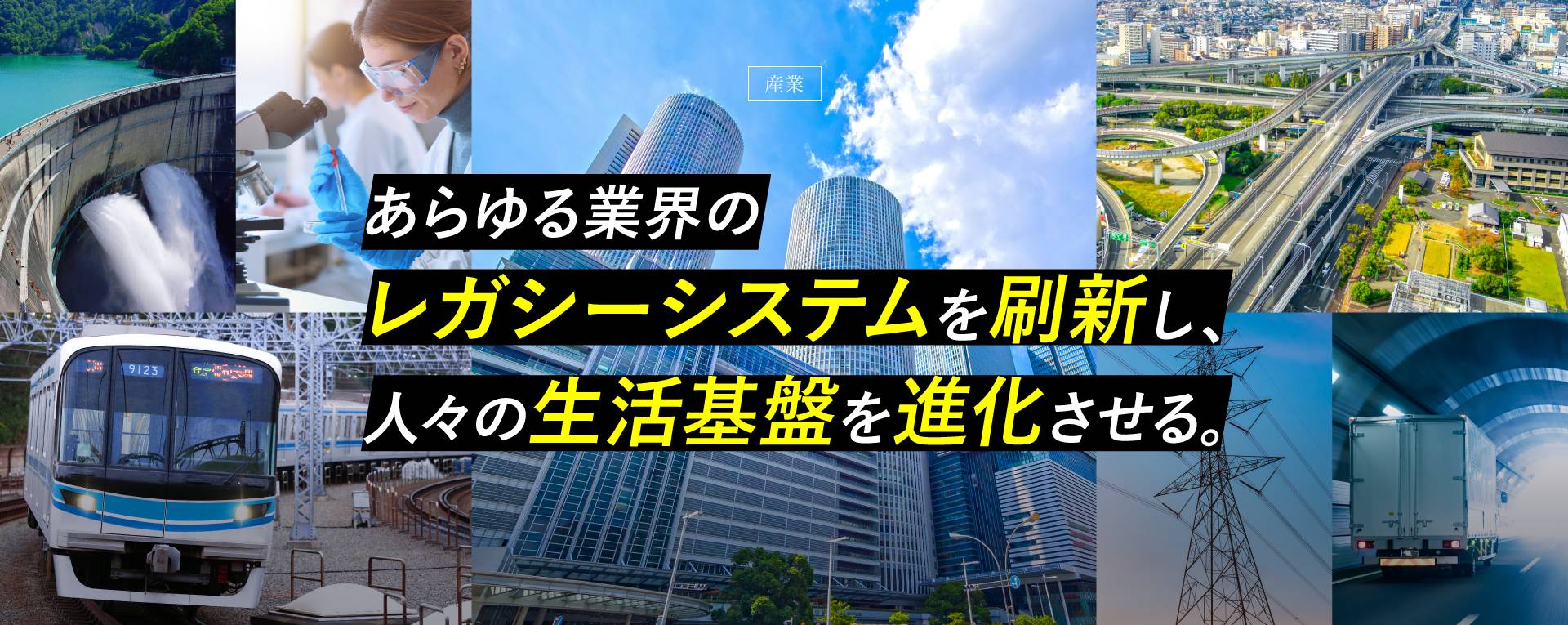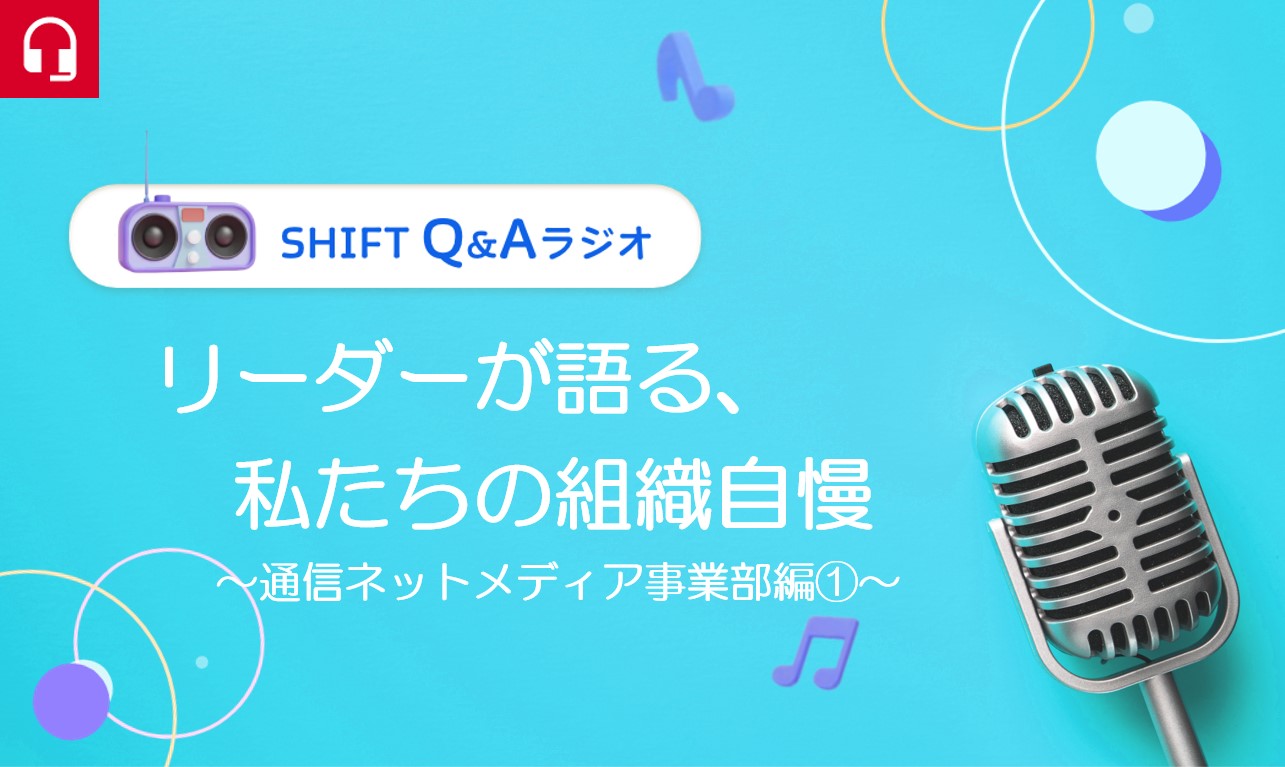「通信ネットメディア事業部は、SHIFTのDNAがもっとも色濃い事業部ではないでしょうか」
通信ネットメディア事業部 事業部長 能代谷 亮は、誇らしげに語ります。
同部は、その名の通り、大手通信企業やBtoCを含めた各種インターネットサービスを手がけるお客様に向き合う事業部です。
テストをはじめとする下流工程はもちろん、要求整理、要件定義、製造に関するドキュメント支援からはじまり、プロジェクトの改善コンサルティングといった上流工程の支援まで担っています。
「SHIFTのDNA」とはどのようなものなのか、また品質を軸に上流工程から開発、運用までクロスセルを手がける原動力とは。能代谷をはじめとした3名の部長職メンバーに、通信ネットメディア事業部の「リアル」を聞きました。
-

通信ネットメディア事業部 事業部長 能代谷 亮
2010年に大手SIerに入社。営業として製薬、通信、メディア業界にて新規開拓から既存深耕まで幅広い案件を担当。その後、IT機器の輸入代理店業務を経験し、2019年SHIFT入社。営業として新規顧客を担当、入社初年度にSHIFT AWARDにて全社で一名のみが選ばれる新人賞を受賞。2021年に通信営業グループ長就任、2023年に通信メディアアカウントマネジメント部長就任、2024年から通信ネットメディア事業部事業部長として組織運営に従事。
-

通信ネットメディアサービス部 部長 清信 圭太
前職はSIerにてオープン系開発エンジニアとして従事、その後Webサービス関連の受託案件にて、SHIFT現上席執行役員兼人事本部長の菅原要介と同じ案件で関わるようになり、菅原の人柄、いっしょに仕事をしたいという想いのもと2012年SHIFT入社。Web系、ゲーム系、パッケージ系、IoT系など多種多様なプロジェクトに新規参画し、立ち上げを経験。PM、スクラムマスター、品質コンサルなどを経てラインマネジメント、2021年にネットサービス部(現 通信ネットメディアサービス部)の部長に就任し、組織運営に従事。
-

通信ネットメディア営業部 部長 高見沢 友成
2012年、大学卒業後、大手食品メーカー入社。営業職として複数社経験後、異業種ポテンシャル採用枠として2018年SHIFT入社。IT/Web業界などネット大手をはじめとするデジタルビジネス業界全般のお客様を中心に既存アカウント営業、新規開拓を担当。その後、2021年より複数営業グループのグループ長を経験後、2023年ハイテク・メディアサービス営業部 部長に就任、2024年から通信ネットメディア営業部 部長として売上予算の達成や組織運営に従事。
目次
SHIFT“らしさ”とは何か
――まずは、通信ネットメディア事業部について教えてください。SHIFTのなかで、もっとも人数が多い事業部だそうですね。
能代谷:はい。人数は約1,200人、2024年12月時点で10ある事業部のなかで最大です。売上も社内最大で、今期の売上目標約180億円を目指しています。
もっとも、それは事業部の定量的な特徴でしかありません。むしろ“定性的”な特徴こそ、私たちの誇りなんですよ。
――といいますと?
能代谷:一人ひとりがバリューを能動的に発揮してお客様に貢献し、業績を伸ばしていること。また、そうした意識が、部のミッションとして根づいていることです。
「自分は営業担当だから」とか「サービスデリバリー担当だから」などと部署や職域に関する垣根を設けることなく、全員がコミュニケーションを頻繁にとっています。
さらに、自分の眼の前の仕事や成果ではなくお客様に目を向け、最善策を考えて行動できる。だからこそ、高い売上をあげられています。
高見沢:これが「SHIFTらしさ」ですよね。
いまでこそ連結の従業員数が13,000人ほど(2024年11月末時点)に増えたSHIFTですが、私が入社したころは、まだ従業員が数千人。ベンチャー企業としての活気が溢れていて、規模が小さい分、風通しも相当よくて。
その後、会社全体が巨大化すると同時に、コロナ禍もあり、リモートワークも増えました。結果として、世の企業がそうだったようにSHIFTでもビジョンの共有が希薄になりがちだった時期もありましたね。
清信:我々3人はとくに上下関係のないカルチャーが染みついているメンバー。高い熱伝導で思いと情報を共有しながら、お客様に向きあってきた自負がありましたよね。
そうした「SHIFTらしさ」がいま、2024年9月からの新年度の組織編制を経てまた色濃いものになってきました。
営業とデリバリーを一体化した「通信ネットメディア事業部」として、互いの情報をシェアしながら、「お客様ごとにどんな困りごとを抱えているか」「課題をどのように解決できるか」をそれぞれが能動的に考えて行動する一枚岩のチームが再び戻ってきたことを実感しています。
能代谷:ちょうど私がSHIFTに入社した5~6年前、全社の売上が190億円ほどでした。
現在では、通信ネットメディア事業部単体でも同程度の売上に届きつつある。そう考えると、通信ネットメディア事業部はベンチャー的な高い熱量をもった当時のSHIFTそのものという感じがしますね。

テスト領域から、お客様とともに成長してきた
――お客様の業界は、EC、マスメディア、教育など非常に多岐にわたりますよね。
能代谷:はい。共通しているのはほとんどのお客様が「BtoC」の領域を手がけていることです。
基本的には一般の生活者・消費者がエンドユーザーとなるサービスを展開しているお客様のプロジェクトに参画して、テストや品質保証、上流工程の開発支援をしています。
清信:もともとSHIFTのテスト事業はこうしたWebサービス業界を皮切りに、他業界へと広がっていきました。支援領域についてもテストで成果をだすことで、開発などの上流工程まで広がっています。
――いま伴走しているお客様は、どのような課題を抱えていますか。
高見沢:目立つのは以下の3つです。
1つめは「エンジニア不足」。特にBtoC向けの業界は、人材の流動性が高い印象があります。そのため、業務効率化やアウトソーシングのニーズは高まる一方です。
2つめは「属人化への対処」です。人材の流動化が激しい一方で、属人化されたシステム、プログラムが多くなっています。
つまり、そのシステムを手がけた人がいなくなった途端、「同じ言語を使える人がいない」といった事態に陥っています。結果として、システムの品質低下などの問題を抱えているお客様は少なくありません。
――なるほど。最後の1つは?
高見沢:「開発速度の高速化」です。Webアプリやサービスなどは、ユーザーの声を反映するためにアップデートが頻繁に行われます。
つまり、開発スピードが求められるのです。臨機応変に対応でき、作業スピードもはやく、質の高いシステムの設計、構築、運営というエンジニアリングのニーズが日々高まっているのを感じます。
清信:上記の3つの課題に関して、SHIFTは他社よりも圧倒的な価値を提供できています。

システムやサービスの「健康診断」ができるのは、我々だけ
――その理由はどこにあるのでしょうか。
清信:どこよりも多彩な知見をもっているからです。
SHIFTはこの業界に古くから多くの取引先をもち、テスト・品質管理を行ってきました。累計でいうと、数万におよぶプロダクトや数千以上のプロジェクトに携わってきました。
多彩なプロジェクトに参画してきたからこそ、ノウハウが蓄積されている。
そのため、プロダクトの品質やプロジェクトの進め方の良し悪しが客観的に判断できるし、改善できるわけです。
――積み重ねてきた実績があるからこその対応力ですね。
清信:我々が行っているのは、システムやサービスの「健康診断」に近いと思うんです。いくら正確な検査をしても平均値が貧弱であったり、サンプル数が少なかったりすれば意味がありませんから。
高見沢:大抵のベンダーやSIerは、テストを積極的にやりたがりません。彼らにとっては設計や運用が業務の柱。テストはあくまでそれに付随するものに過ぎないからです。
SHIFTは違います。大手SIerと遜色ない提案能力をもちながらも、「テスト業務を積極的に請け負いたい」と考えています。
清信:テストの品質が圧倒的に高いという自信がありますよね。「エンジニア不足」に見舞われているなかでも質の高いシステムの開発や改修に効率的にコミットできる、という。
「我々が参画したからには、品質は担保される」安心感を提供したい
――属人化されたシステムへの対応は、どのように行っているのでしょうか?
高見沢:それこそ我々の得意領域です。テストを行う際には、必ず「テスト設計書」を起こします。
これは、正確なテストを実施するため、ひいてはお客様の業務やシステムを整理するためのドキュメントです。ドキュメントの精度は極めて高く、お客様がそのまま仕様整理に使えるほどです。
――SHIFTが入ることで、お客様は属人化されたシステムを改めて整理できるわけですね。
高見沢:そのとおりです。例えば、ある不動産系Webサービスを展開するお客様は属人化されたシステムを運用していました。異なるエンジニアが何度も改修した結果、継ぎ接ぎだらけの不安定なシステムになっていたのです。
テスト設計書をつくり仕様が整備できた結果、「今後の改修の工数を大幅に減らせる」という声をいただいたり、「社内のシステム関連の問いあわせ対応もSHIFTに任せたい」という依頼にもつながったりしました。

――仕様が整備されるとお客様が内製できるようになる。SHIFTの仕事がテスト止まりになって機会損失になりませんか?
高見沢:むしろ、ベンダーコントロールやプロジェクトの設計など上流工程の領域もご依頼いただくことが増えています。
テスト設計をする過程で、私たちがお客様よりも仕様を理解しているとさえいえる状態になっているので。
能代谷:ITベンダーからも「SHIFTとプロジェクトを提案したい」といった声を多くいただきます。ユーザー企業とITベンダーの橋渡しができるのも、我々の強みだと思いますね。
高見沢:最近は、競合企業がテスト専門会社ではなく、コンサルティングファームなどに移行しつつあります。どこよりも前向きにテストしつづけた結果、上流工程のノウハウが蓄積された稀有な組織です。
清信:テストや設計、プロジェクトの進行において、私が描くゴールイメージは「お客様に品質を忘れてもらう」ことです。
SHIFTが入ったからには、品質が担保される。お客様は品質にまつわる課題にリソースを使うことなく、サービスの向上に努められるのです。
貢献が認められる好循環の中で、自身のポテンシャルを最大限に発揮できる
――質の高い仕事を提供しようとすると、メンバーに求めるレベルも高くなりますよね。
能代谷:実際、向上心の高いメンバーが集まっています。
私たちのチームにいると、お客様の課題解決に役立つ多彩な業務を自ずと手がけられる。エンジニア、営業、デリバリーなど担当を問わず、メンバー全員が頭を使って仕事のレベルを上げつづけられます。
また、好循環のなかで自分のポテンシャルを最大限に発揮できます。まず、お客様が抱えている課題の解決はDXを推進すること、社会に新たな価値を生み出すことに直結します。
そして、課題解決に貢献した人材はキャリアや年齢などは関係なく正当かつ高く評価されて、給料や職級が上がります。
――どのような人にジョインしてほしいですか?
高見沢:やはり自分の頭で考えることをあきらめない人、実際に動ける人でしょうか。特に営業はただモノを売るのではなく、さまざまなお客様に提案していく必要があるので。
清信:そうですね。評論家ではなく、実務家が成長しています。
能代谷:とにかく、さまざまなチャレンジをしていける人。
「本当はここまで手がけてみたい」「お客様にこんな提案ができたら…」という理想がある人、あるいは「正当に評価されたい」と考えている人は、ぜひ我々のグッドサイクルに入っていただきたいですね。
※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです