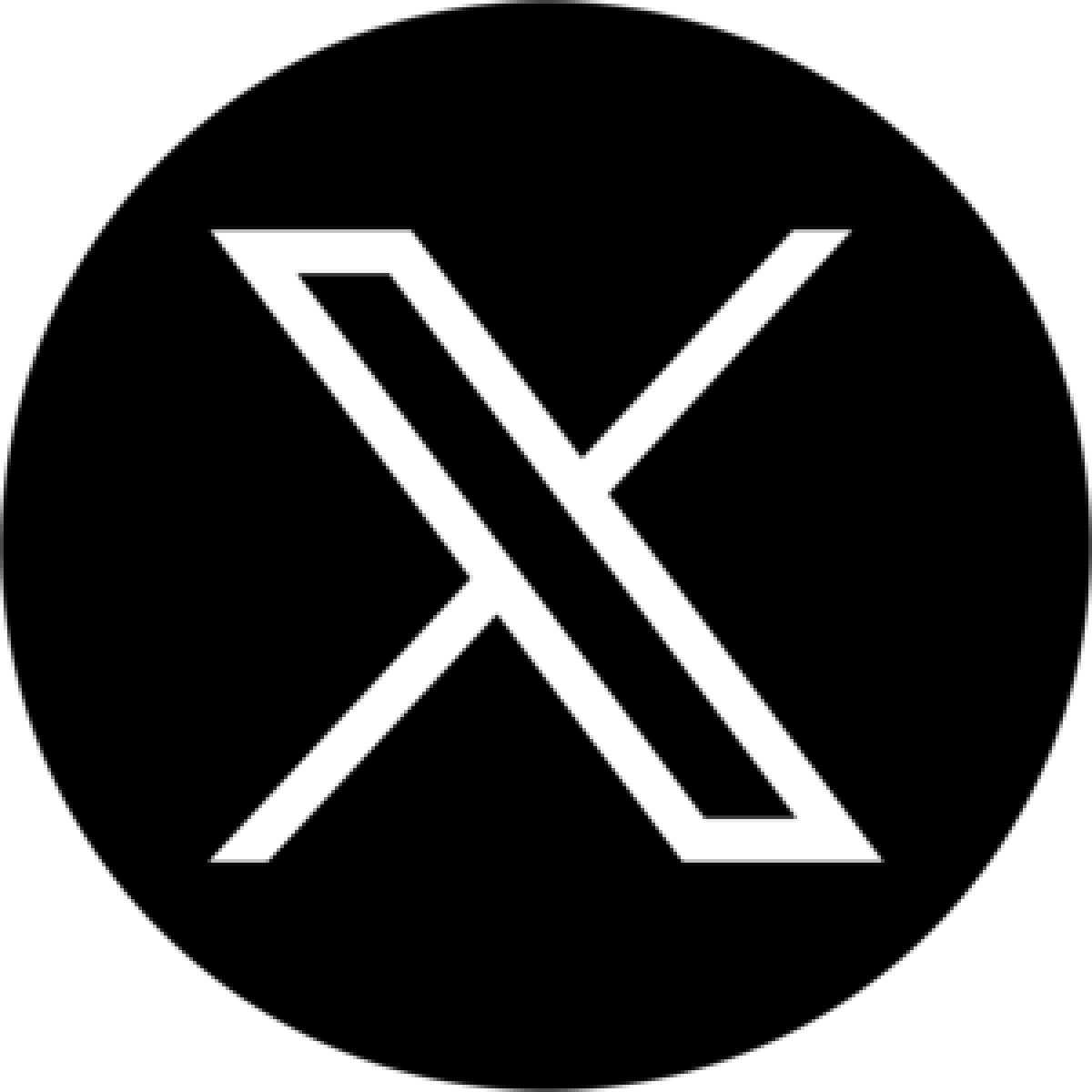「売上高ですか?初年度に比べ、文字通り“桁違い”に伸びています」
さらりと語るのは、カスタマーサクセス部で部長を務める綿貫 健吾です。
SaaS市場の拡大とともに、一気にビジネスシーンへ浸透したカスタマーサクセス。
お客様を成功に導くことで、企業の顧客生涯価値(CLTV)を向上させるのが主目的ですが、カスタマーサポート領域においては、コストセンターというイメージが強いのも事実。 ですがSHIFTでは、利益を生み出す部署として年々存在感を増しています。
快進撃を語る前に立役者である綿貫の、異色ともいえる経歴について触れておきたいと思います。
大学在籍中に大手電機メーカーのコールセンターにアルバイトとして入社。正社員となってまもなく、コールセンターの運用管理者の立場からCRMシステムの刷新プロジェクトにアサインされました。システムと運用をどう融合させ、業務効率化を実現させるのか……思い描いたイメージを形にし、スキルと実績を手にした綿貫は、さらなるキャリアアップを目指してSHIFTの門を叩きました。2017年のことです。
あれから6年。基軸事業である品質保証領域の経験を経て、カスタマーサクセス事業を立ち上げ指揮を執る綿貫に、これまでの歩みと未来への展望について語ってもらいました。
-

カスタマーサクセス部 部長 綿貫 健吾
大手BPO会社に入社以降、コールセンターマネジメント・営業支援・海外事業推進室の経験を経て、2017年にSHIFT入社。2019年には、SHIFTのグループ会社である株式会社SHIFT PLUS代表取締役社長に就任。2021年には、同グループの株式会社エスエヌシーの取締役副社長も兼任。
目次
「本当にこの対応でいいの?」現場担当者の疑問が、ビジネスをつくる
カスタマーサクセス部は2019年、社外向けITヘルプデスクの代行サービスからスタート。以来、カスタマーサポート・UI/UX・CRM運用支援・CRO・情報システムの最適化と徐々に事業領域を広げていきました。
すべてのサービスにおいて共通しているのが、「運用目線」で業務・改善支援をおこなっていること。ただツールをインストールしたり、サービスを開発して終わりではなく、その先の運用に伴走してはじめて、お客様の売上や業務効率化に貢献できると考えているからです。
部署を立ち上げて間もないころ、ITヘルプデスクからIT運用保守へと事業を拡げたのも、同様の発想でした。オペレーター自身の判断・対応が困難な重要事項を、技術者へ齟齬なく申し送りするのは、ITヘルプデスクサービスの範疇では困難。課題に感じていたところ、お客様からも運用やセキュリティに詳しいエンジニアのアサインを求める声が挙がったのです。
そこで、エスカレーション対応をおこなえるIT運用保守サービスを早々にスタート。一気通貫でスムーズに対応できるサービスラインナップを確立できました。
もしかしたら、カスタマーサクセス系の業務に就いている方、もしくは過去に従事されていた方にとっては、これはただの理想論に聞こえるかもしれません。ではなぜ、理想を現実のものにしているのか。
私たちはカスタマーサクセスの現場で働く人が「本当にこのままでいいのだろうか?」と日々疑問に思っていることに事業の軸足を置いています。みなさんの疑問、つまり業界全体の課題を解決に導くことがビジネスチャンスにつながると考えているからです。
ツール導入の先にある「運用」に目を向け、DXを成功へと導く
例えば、Salesforce。導入に関わりお客様から感謝されたものの、肝である運用フォローは別予算のため、プロジェクトは強制終了。後ろ髪を引かれつつ、その場を去った……こんな経験をもつ担当者は少なくないのではないでしょうか。
他方、お客様側は素晴らしい営業ツールをインストールしたものの、どうやって使いこなせばいいのかわからない。残念ながら、こうしたケースは後を絶ちません。
お客様から本当に必要とされているのは、単なるツール提供ベンダーではなく、システムも運用もわかるパートナーです。こうした事実を現場で突きつけられながら、前職ではなす術がなかったと話す社員が、カスタマーサクセス部には数多く存在します。しかし、彼らはいま、水を得た魚のようにいきいきと、やりがいをもって業務に励んでいます。
もともと私たちがSalesforce運用支援サービスをはじめたのは、コールセンターのDXに対して、本質的なサポートをしたいという思いからでした。大切なのは、システムをどのように組みあわせ、どう現場で使いこなしていくかという運用の視点なのではないか──私の直感は的中しました。
昨年からは、企業そのもののDXに目を向けた、事業会社における情報システム部門への支援サービスも開始しました。DXの意義から目的の確認、推進プラン、実施計画まで0からしっかりと伴走し、成功に向けてサポートしています。
私たちはシステム・運用とお客様を結ぶ、いわば翻訳者のような存在なのかもしれません。

グループ会社とのタッグで新たな価値を生み出す
グループ会社と連携できる組織体制も私たちの強みです。なかでも、私が代表を務めるSHIFT PLUSは、当部署が開設される前からカスタマーサポート事業を展開。高知本社のほか、群馬、札幌にも拠点を置き、各地で優秀な保守担当エンジニアを採用している頼もしい存在です。
同社の主力サービスは、カスタマーセンターに届いたユーザーの声を分析し、カスタマーサクセスにつなげるCSデータアナリティクスサービスです。このサービスを用いて、お客様の課題をドラスティックに解決した事例があります。
大手玩具メーカーでは、コールセンターにSalesforceを導入していましたが「本当にちゃんと使いこなせているのか」と日々疑問を感じていました。そこでカスタマーサクセス部では、Salesforce運用支援に、ふたつのサービスを加えて提案。
ひとつはサイトに設置されているFAQコンテンツやチャットボットのUXが適しているかどうかを分析する、UXエキスパートレビュー。もうひとつは、SHIFT PLUSのCSデータアナリティクスサービスです。
コールセンターにどのような問いあわせがあるのかを把握しつつ、それぞれの内容にSalesforceの使い方、サイトのUXの適合性を分析して無駄を可視化する──グループ会社と連携しながら、複合的なプランを提案、実施したことでお客様からは「大きな気づきが得られた」と高評価。コールセンター全体の抜本的な改善のプロジェクト化につなげることができました。
求めるのは、当たり前を疑える人
このプロジェクトを率いたのは、50代の女性社員です。前職の経験からSalesforceに大変造詣が深いうえに、アイデアを形にする力があります。根底にあるのは、「素晴らしい製品群を無用の長物にしたくない」という課題意識。目的に沿った活用法を編み出し、多くの企業に使いこなしていただくことが、自身の励みとなっているようです。
彼女のようにやりたいことが明確であればあるほど、実現可能性が高まる。そんな土壌がSHIFTにはあります。例えば「うちの基軸事業は、ソフトウェアの品質保証やテストなんだから、余計なことしなくていい」などと止める人は、SHIFTにはひとりもいません。
当然ながら、一定以上の成果は求められます。
「ケニア人はなぜ陸上競技に強いと思う?」──過去の会議で代表の丹下が私に問うた言葉です。答えは、ハイレベルな選手が多いから。要は、優秀な人材しかいない環境に入れば、たとえ新参者であっても上へと自然に引っ張られていく、という意味だったのですが、入社してみて納得しました。
企業として長期的な売上目標を公言し、利益率やお客様対応などにおいて、求められる水準が当然のように高い職場。社員一人ひとりの活動量は目に見えてぐんぐん上がっていきます。このような環境に適合できるタイプは、間違いなくSHIFTのカルチャーにフィットするでしょう。
加えて、カスタマーサクセス含め多くの事業において当社は後発企業です。だからこそ王道から少し軸をずらしてアイデアを練らないことには、商機を見出せません。うちの部署においては、「いま、存在しているものって本当に必要なんだろうか?」と当たり前を疑える人、疑問を起点にして新たなサービスをつくれる人をつねに求めています。

SHIFTの飛躍のために、社会のために。カスタマーサクセスができること
いまは品質保証サービスがSHIFTの中枢であり、そこからお客様ニーズを汲み取り、顧客単価を向上させる役割を果たしていますが、ゆくゆくはカスタマーサクセスがエントランスサービスになる必要性があると考えています。当社は急成長をしつづけているからこそ、お客様の声を真摯に受けとめ、各事業に活かすことが、さらなる飛躍のカギとなるからです。
例えば、お客様の声をカスタマーサクセス部で分析して、その結果から品質テストや開発部署にクロスセルを促す。すると「SHIFTはユーザーの声をしっかり受け止め、提案してくれる」という印象につながり、やがてロイヤリティを高められる。そんな可能性を感じています。
カスタマーサポート事業に従事するメンバーはグループ全体で約400名にのぼります。今後、規模はさらに拡大するでしょう。
いまいる仲間、そしてこれから入社いただく方々と共に、引きつづき、現場担当者の課題に耳を傾けつつ、新たなサービスを開発していきたいですね。
外部協力:福嶋 聡美(執筆)
(※本記事の内容および取材対象者の所属は、取材当時のものです)
この記事のタグ