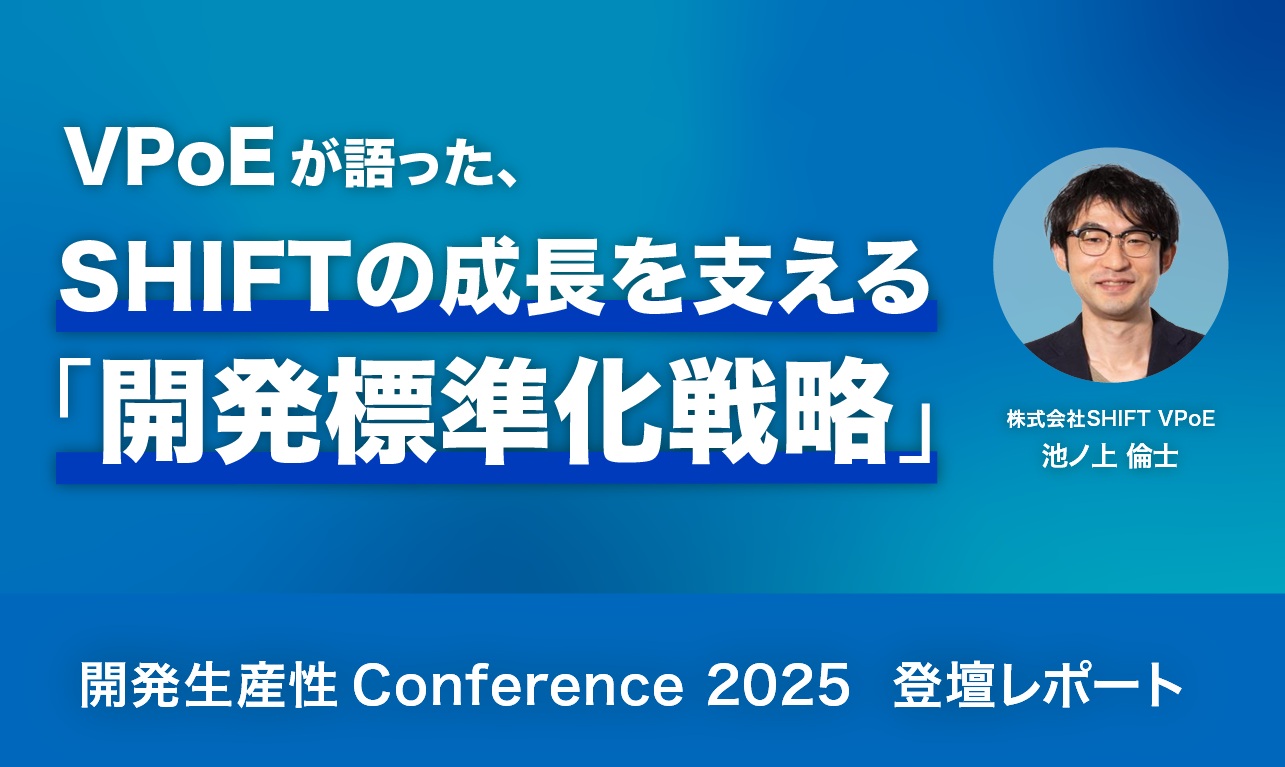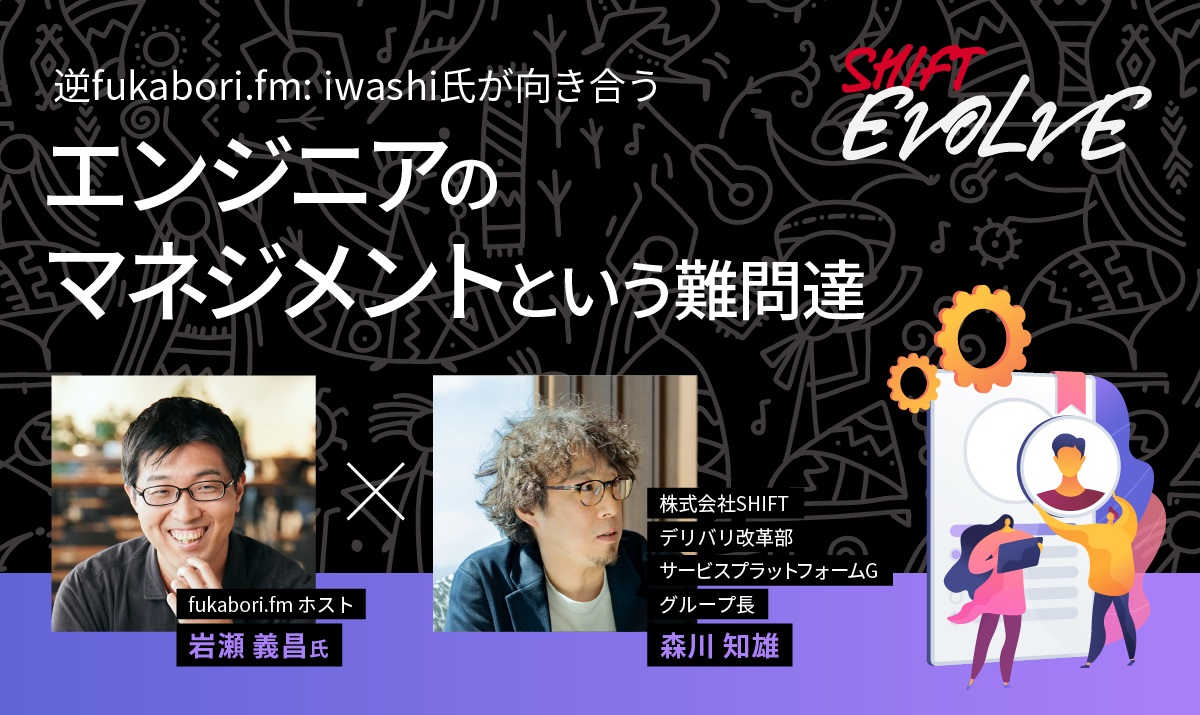
2025年8月20日、SHIFTが手がける技術イベント「SHIFT EVOLVE」にて「逆fukabori․fm: iwashi氏が向き合うエンジニアのマネジメントという難問達」と題したセッションを開催しました。
当日は、エンジニアに人気のポッドキャスト「fukabori.fm」のホスト・iwashi(岩瀬 義昌)氏をゲストに迎え、 SHIFTのエンジニアリングマネージャー(EM)である森川が、iwashi氏のEMとしての日常や仕事観について深掘りしました。
本イベントレポートでは、特に印象的だった部分をお届けします。
-

fukabori.fm ホスト 岩瀬 義昌(iwashi)氏
エンジニアに人気のポッドキャスト「fukabori.fm」を運営。
本業では大手通信事業者にて、大規模IP電話システムの開発、内製、アジャイル開発、人事などの業務に従事後、現在はGenerative AI ProjectのLeaderを務める。
そのほか、『エンジニアのためのドキュメントライティング』『エレガントパズル エンジニアのマネジメントという難問にあなたはどう立ち向かうのか』『エンジニアリングが好きな私たちのためのエンジニアリングマネジャー入門』を翻訳。 -

サービスプラットフォームグループ グループ長 森川 知雄
中堅SIerにて品質管理業務を担当。テスト戦略から人材育成までを担当する。テスト自動化技術Seleniumに出会い、テスト自動化ツールをスクラッチ開発し、テストコストを最大40%削減。以後、テスト自動化~DevOpsといった技術に将来性を感じる。2019年、新しいことに挑戦できる環境を求めてSHIFTへジョイン。統合型ソフトウェアテスト管理ツール「CAT」やテスト設計支援ツール「TD」の開発・運営を担うCAT推進室 室長を経て、2023年9月より現職。
目次
数式でひも解く、EMの本質
森川:まずは、基本的な質問から。岩瀬さんの考えるEMとは何でしょうか?
岩瀬:僕の考えるEMとは、「いろいろなマネジメント手法を使いわけて、会社や組織の求める成果を出す人」です。
これはマネジメント職すべてに当てはまることだと思っていて、EMでもプロジェクトマネージャー(PM)でも変わりません。
森川:EMConf JP 2025で、岩瀬さんが組織のアウトプットを数式で表していましたよね。これが非常に興味深かったので、改めてご説明いただけますか?
岩瀬:「組織のアウトプット = (メンバーの能力 × メンバーの熱量)―摩擦・制約」ですね。この数式はオリジナルのものではありませんが、非常に的を射ているので使いつづけています。
森川:この数式の意味を、くわしく教えてください。
岩瀬:まず、チームの成果はメンバー個々の「能力」に、仕事への「熱量」をかけ合わせることで生まれます。
どれほど優れたエンジニアがいても、やる気がゼロなら成果を出すことはできません。逆に、熱量があっても能力が伴わなければ、成果をあげることはむずかしい。熱量と能力は、成果の源泉です。
そして、組織にはどうしても「摩擦・制約」が存在します。例えば、他部署との連携、全社共通のルール、大企業にありがちな承認プロセスなどですね。
これらが増えるとマイナスの影響が大きくなるので、いかに減らすかが重要です。つまり、EMの仕事は「能力と熱量を高めて成果を増やし、摩擦や制約を減らす」ことだと、この式は示しています。
森川:この数式で「引き算」の発想を加えたのは面白いですね。通常、多くの人は「能力を上げる」「モチベーションを上げる」というかけ算の部分にフォーカスしがちですが。
岩瀬:そうなんです。実はこの「引き算」は、EMの仕事として非常に重要です。いくら能力と熱量が高くても、組織の摩擦や制約が大きければ成果は出にくくなります。
シチュエーショナル・リーダーシップで能力を育てる
森川:「メンバーの能力」を伸ばすために、どんな工夫をしていますか?
岩瀬:「シチュエーショナル・リーダーシップ理論」という考え方が参考になると思います。これは、メンバーのレベルによって接し方を変えるというものです。
例えば、新卒とベテランに対して、同じように接することは望ましくありませんよね。
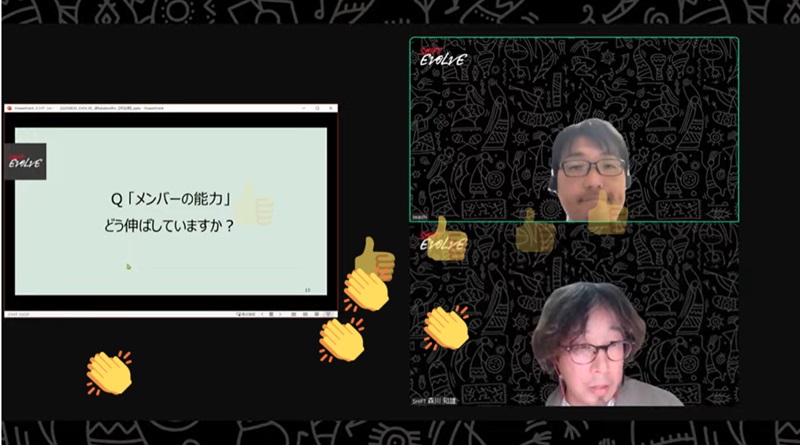
これから能力を習得する方に対しては、ベースラインを身につけてもらうためにキャリアの考え方や技術の習得方法を伝えます。一方、ある程度経験を積んできたシニアクラスの方に対しては、コーチングスタイルで接します。
森川:自分より高い専門技術をもっているメンバーに対しては、どう接していますか?例えば、多岐にわたる技術を扱っている場合、マネージャーとしては把握・管理がむずかしいのではないでしょうか。
岩瀬:ちょうどいま私たちのチームが置かれている状況ですね。私は工学を専門としてきたので、言語処理や機械学習に関しては、それを専門としてきたメンバーの方が理解度も解像度も高いです。
ただ、私自身ソフトウェア開発への理解はありますし、機械学習などについても基礎理論などは把握したうえでメンバーと話すようにしています。
そうすると、メンバーも「わかってくれている」「勉強してくれている」と認識してくれるので、コミュニケーションに困ることはありません。
モチベーションを引き出す、ポエムドリブンマネジメント
森川:次は、「メンバーの熱量」について。メンバーのモチベーションを高めるために、どのようなことを意識していますか?
岩瀬:メンバーの熱量を無理にあげるというよりは、各メンバーの興味関心(モチベーションが自然と上がるもの)を考慮して案件や業務へアサインしています。
「論文などアカデミックな方面で頑張りたい人」もいれば、「顧客への価値提供に全力を注ぎたいビジネス志向の人」もいます。
そのため、1on1などを通じてその人のタイプをちゃんと把握し、そのうえで適したタスクを任せると、熱量は自然に高まっていく気がします。
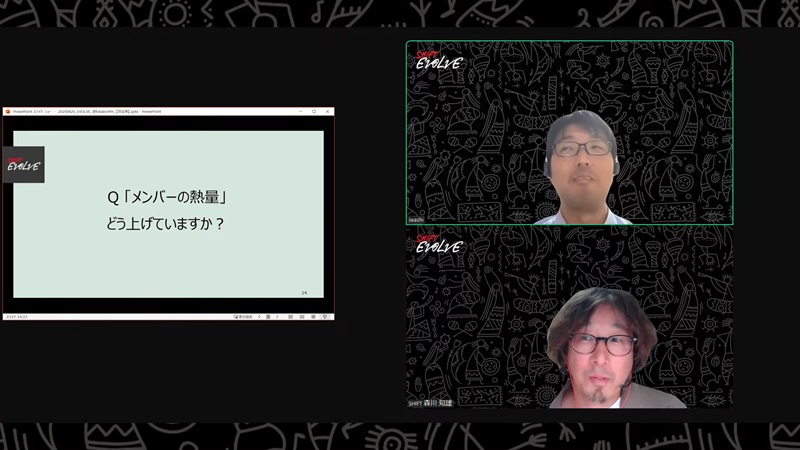
森川:個々の熱量を引き出す一方で、チーム全体の方向性を合わせる「ベクトルの調整」も重要だと思います。
例えば機能追加でビジネス寄りのゴールを目指すときに、アカデミック志向の人がいると方向性の調整がむずかしそうです。このあたりはどう対応されていますか?
岩瀬:そのような時は、「ポエムドリブンマネジメント」を実践しています。
「こういう背景があって、こういうところにたどり着きたい。そのためにチームではこんなものをつくるんだ」という「想い」の部分を、Notionなどにしっかり書き残しておくんです。
業務指示や仕様書ではなく、思考を透明化・可視化するイメージですね。
森川:メンバーからの反応はいかがですか?
岩瀬:反応があるものとないものがあります。Notionなどのツールだと文章をハイライトしてコメントを書くことができるので、メンバーがコメントをくれることも多いです。
「信頼貯金」で摩擦を減らす
森川:1on1でメンバーから本音を引き出すには、信頼関係が不可欠だと思います。阻害要因などを正直に話してもらう関係性は、どうやって築いているのでしょうか?
岩瀬:アプローチは2つあります。1つは、私自身が徹底的に自己開示すること。「私はこういう価値観で仕事をしています」「いま、これで困っています」と自分の考えをしっかり伝えることで、相手も開示しやすくなります。
もう1つは、メンバーがブロッカーを話してくれたら、感謝して、一生懸命それをとり除くことです。
「この承認プロセスが面倒くさい」といった小さなことから、人事へのかけ合いといったマネージャーでないと解決しにくいことまで、全力で手伝います。
これを繰り返すことで、マネージャーとしての「信頼貯金」が貯まっていきます。
森川:いよいよ数式の「引き算」の部分、「摩擦・制約」を減らす仕事術についてです。どのようなアプローチをしていますか?
岩瀬:摩擦を減らすアプローチには、ミクロとマクロの2つがあります。ミクロなアプローチは、まさに1on1で日々の阻害要因を聞き、とり除くことです。
「この事務処理が進まない」といった声があれば、僕が解決したり、社内の専門家へ橋渡しをしたりします。
マクロなアプローチは、個人ではどうしようもない、全社的なルールや硬直化したプロセスに挑むことです。
例えば、情報セキュリティのプロセスやリリースのための審議などですね。経緯を考えれば妥当でも、現代の開発スタイルには合わなくなっているものが増えてきます。
そうした大きな壁に挑むときは、そのプロセスのオーナーに直接話をしに行く必要がありますが、一メンバーが行くのは大変です。
そこはEMとしてまわりを巻き込み、斜めのネットワークも使い、あの手この手で物事を前に進めていきます。
森川:岩瀬さんは以前、会社にアジャイル開発を広めたり、著名な方を技術顧問として招聘したりと、大きな組織変革を主導されましたよね。
岩瀬:僕ひとりでやったわけではありませんが、それも摩擦を減らすアクションの一例ですね。
アジャイル開発をやりたいのに、既存のウォーターフォール用のルールしかない。それなら、新しい仕組みを立て直す必要があります。
森川:技術顧問の招聘は、どのように実現したのでしょうか?
岩瀬:外部のエキスパートを呼んできて、自分の会社の幹部層に話をしてもらいました。
プロダクトマネジメントの及川 卓也さん、アジャイル開発の吉羽 龍太郎さん、テスト駆動開発の和田 卓人(t-wada)さんに顧問になっていただきました。
森川:「よくOKが出たな」というのが率直な感想です。何か秘訣はあったのでしょうか?
岩瀬:大きかったのは、人事部門に強力な協力者がいたことです。私の取り組みをものすごく評価してくださり、「岩瀬がいっていることには価値がある」と説明して、決して安くない稟議を通してくれました。
なぜ協力してくれたかというと、それまでの技術ブログの発信やDevRel活動など、日々の活動で社内での「信頼貯金」が貯まっていたからだと思います。
「あの人に任せておけば大丈夫だ」という信頼が、大きな壁を動かす力になったのでしょう。
成果は運も含む?EM評価のむずかしさ
森川:EMの評価はどのように行われるべきだとお考えですか?
岩瀬:身も蓋もない回答になってしまうかもしれませんが、EMの評価は成果とほぼイコールだと思っています。
先ほどもいいましたが、いろいろな手段を使って成果を出すのがEMですので、その成果が出ているか否かが評価の基準です。
森川:チームの成果とEMの評価が連動するということですね。
岩瀬:そうですね。「みんなで心中する」感じです。成果が出なければチーム全員が悪い評価を受けますし、成果をあげれば全員がいい評価を受けます。
「サボる人がいたらどうするの?」とよくいわれますが、私のまわりでは「みんな頑張る」という前提で評価が運用されていますね。
森川:たまたま成果が出たのか、EMのおかげで成果が出たのかわからないときもありますよね。
岩瀬:正直、業績評価や成果といったアウトカム、特に利益に関わるものは、運の要素が大いに関わっているなと思っています。
「いい」市場に入り込んでいれば、多少変わったものをつくっても売れてしまうことがありますから。
発信を通じて広がる学びの循環
森川:岩瀬さんは好奇心をもってつねに学びつづけていると思いますが、好奇心の強さはチームメンバーにも求めますか?
岩瀬:自分のチームに入れる人は自分で採用することが多いのですが、その際には僕特有の観点で人を評価しています。その1つが「好奇心の強さ」です。技術を熱く語れて、技術を楽しめる人にきてもらうようにしています。
森川:ご自身の成長についてはどうでしょう?この1年間で成長したと感じることはありますか?
岩瀬:この1年間の成長でいうと2つあります。1つはテクノロジー面にくわしくなったことです。
機械学習系のマネージャーをしているので、例えばTransformerの中身や生成AIの仕組みについて解像度が高まりましたし、ある程度コードも書けるようになりました。
もう1つは、委譲がうまくなったことです。以前は自分で手を動かしたくなってしまう傾向があったのですが、この1年間でうまく委譲できるようになりました。
「再現性のある発信」を意識して発信しつづける理由
森川:岩瀬さんはポッドキャストや執筆活動を通じてご自身の経験を積極的に発信されていますが、つねに再現性に留意していらっしゃるようにみえています。最後に、その動機と理由をお伺いしてもいいでしょうか。
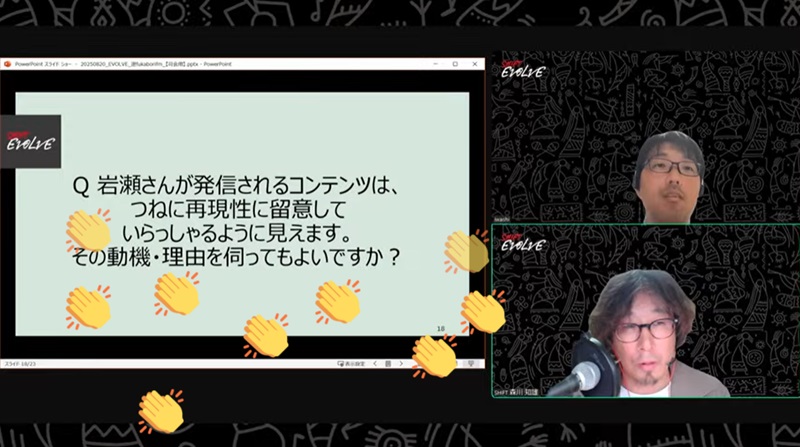
岩瀬:これは具体と抽象の話だと思っています。例えば私のチームでうまくいった事例は、抽象化するとほかのチームでもうまくいく可能性が高いですよね。
Aチーム、Bチーム、Cチームの事例を抽象化してXというパターンがみえたら、それをDチームにうまく展開できる、といったように具体と抽象をうまく行き来できるように意識しています。
森川:以前、EMには正解がないが、共通の抽象概念があるという話をされていましたね。「ツールボックス」という表現を使われていたと思います。
岩瀬:困ったときに開けるツールボックスには、少なくとも何か入っていた方がいい。入っていたアイデアは特定の文脈でしかうまくいかないかもしれませんが、カスタマイズすればうまくいくものはたくさんあります。
本やポッドキャストで発信する際に、根底にあるのは「この環境ではうまくいったアプローチだけど、あなたの環境ではうまくいかないかもしれない。でも一応伝えておきますね」という考え方です。
EMの仕事に唯一の正解はありません。ツールボックスの中身を少しでも増やしておくことも、仕事の1つといえるかもしれませんね。
(※本記事の内容および取材対象者の所属は、イベント開催当時のものです)